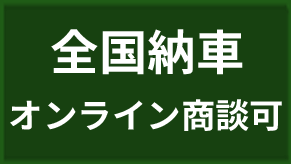同じVWなのに、国が変わると名前が変わる。フォルクスワーゲン“海外での呼び名”図鑑(ビートル/ゴルフ/ジェッタ/パサート)
フォルクスワーゲン(VW)の面白さは、ボンネットの中身だけじゃありません。国境を越えた瞬間、同じクルマが別の名前で呼ばれ、別の人生を歩み出す。その“呼び名の違い”には、文化と市場、そしてVWのしたたかな戦略が詰まっています。今回は海外Wikipedia(英語版)を軸に、クルマ好きの心をくすぐる「海外での呼び名」トリビアを、マニアック寄りにまとめます。■1:ビートルは「正式名称」すら後から付いた。世界中が勝手に愛称を付けたクルマ空冷の丸い背中は、どこの国でも“虫”に見えた。ビートル(Type1)は、1968年に公式に「Beetle」と名付けられたとされ、語源はドイツ語の「derKäfer(甲虫)」です。ウィキペディアつまり、世界が先に愛称で呼び、メーカーが後から“追認”した側面がある。ここがもう、ビートルというクルマの強さです。さらに面白いのが、新しい世代のビートル(A5)でさえ、国によって別名で売られている点。A5は「Käfer(独)」「Coccinelle(仏)」「Maggiolino(伊)」「Fusca(葡語圏など)」といった名称でも販売された、と明記されています。ウィキペディア同...