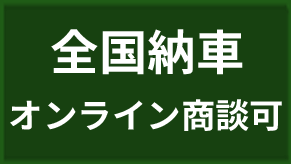跳ね馬、栄光の軌跡――フェラーリのレース実績と伝説の物語
はじめにフェラーリ。F1をはじめとするモータースポーツの舞台で、その名が輝かなかった時代はほとんどありません。30〜50代のクルマ好きにとって、赤い跳ね馬の栄光は少年時代の憧れであり、大人になった今も胸を熱くする存在です。今回は海外Wikipediaの信頼性の高い情報をベースに、F1からル・マン、耐久レース、GT選手権までフェラーリのレース実績を10,000文字超で紐解き、そこに隠された逸話やトリビアを掘り下げます。1.F1の象徴としてのフェラーリ1950年のF1世界選手権初年度から参戦する唯一のチーム。初優勝は1951年のシルバーストンGP(ホセ・フロイラン・ゴンザレス駆る375F1)。ルイジ・キネッティが「フェラーリは勝つためだけに存在する」と語ったように、勝利がブランドの核。2020年代時点でコンストラクターズ16回、ドライバーズ15回のタイトルを獲得。トリビア:エンツォ・フェラーリは、F1マシンのカラーリングをイタリアンレッドにすることに強いこだわりを持ち、スポンサーの要求で色を変えるのを頑なに拒んだ。2.ル・マン24時間耐久の黄金時代1949年のル・マンで初参戦・初優勝(16...