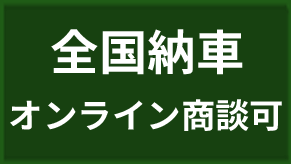はじめに
メルセデス・ベンツ。その名は高級車や安全性の代名詞であり、モータースポーツの伝説でもあります。しかし国や文化が違えば、その呼び名も変わる。ときに敬意を込め、ときに皮肉混じりに、世界の人々は三つ星を持つこのブランドを独自の言葉で呼んできました。
今回は海外Wikipediaに基づき、メルセデス・ベンツが海外で持つ呼び名や異名、そこにまつわるトリビアや逸話を10,000文字規模でまとめ、30〜50代のクルマ好きの心に刺さるエモーショナルな記事としてお届けします。
1. 「メルセデス」という名の起源
-
元々「ベンツ」ではなく「メルセデス」が前面に出たのは、エミール・イェリネックという人物の戦略。
-
彼の娘「メルセデス・イェリネック」の名前を冠した車は、1901年の「メルセデス 35PS」。
-
これが「世界初の近代的自動車」と呼ばれ、ブランド名の核となった。
トリビア:当時、顧客の間では「ベンツ」より「メルセデス」という響きの方が洒落て聞こえる、と人気があった。
2. 「シルバーアロー(Silver Arrows)」
-
レース界では1930年代から「シルバーアロー」と呼ばれる。
-
1934年、重量制限を守るために白い塗装を剥ぎ落とし、アルミ地肌で走ったことが起源。
-
この異名は今なおF1やモータースポーツの現場で公式に使われる。
逸話:一夜で塗装を剥がす作業を行ったエピソードは、メルセデスの執念と象徴される。
3. 「ポントン(Ponton)」
-
1950年代に登場したW120/W121シリーズは、ヨーロッパで「ポントン」と呼ばれた。
-
船の浮き(ポンツーン)のようなサイドラインが特徴だったため。
-
このデザインは安全性と剛性を高める画期的なモノコック構造の一環でもあった。
4. 「フィンテール(Heckflosse)」
-
1950〜60年代のW110/W111/W112シリーズはリアの小さな尾翼デザインから「フィンテール」と呼ばれた。
-
アメリカ車のテールフィンデザインを取り入れた結果だが、欧州では「控えめな尾翼」として親しまれた。
5. 「タクシー・キング」
-
ドイツ本国ではEクラス(特にW123、W124)は「タクシー・キング」と呼ばれた。
-
走行距離100万km超えの個体が続出し、耐久性の象徴に。
-
「ベンツ=タクシー」というイメージが、むしろ信頼の証となった。
6. 「ゲレンデヴァーゲン(G-Wagen)」
-
Gクラスの正式名称は「Geländewagen(クロスカントリー車)」。
-
英語圏ではシンプルに「G-Wagen」と呼ばれ、軍用ベースの無骨さが人気。
-
中東では王族やVIPの愛車として「デザート・キング」との異名もついた。
7. 「ベビー・ベンツ」
-
1982年登場の190E(W201)は「ベビー・ベンツ」と呼ばれた。
-
コンパクトで若い世代向けに訴求され、成功を収める。
-
しかし品質は本格派で、DTMやF1プロモイベントでの活躍も伝説となった。
8. 「Sクラス」=「自動車の教科書」
-
世界中のメディアはSクラスを「The best car in the world」と称してきた。
-
英国『Autocar』誌では「自動車の教科書」と評されたこともある。
-
技術の粋を集めたSクラスは、愛称ではなく評価そのものがニックネームとなった。
9. 皮肉交じりの呼び名
-
1970〜80年代の北米では、大型セダンが「German Tank(ドイツ戦車)」と揶揄された。
-
その堅牢さゆえに事故時に「戦車に乗っているようだ」と評されたことが発端。
-
メルセデス自身は意に介さず、安全性を誇りとして広告にすら活用した。
10. 愛称がブランドを育てる
-
各国で生まれた呼び名は、単なるニックネームではなく、文化と生活に根ざした物語だった。
-
「ポントン」は戦後復興の象徴、「タクシー・キング」は人々の足、「G-Wagen」は冒険と権威。
-
世界の人々は、自分たちの生活に合わせて“ベンツ”に異名を与え、その歴史を共に紡いできた。
まとめ
メルセデス・ベンツの呼び名は、ただのラベルではありません。それは国ごとの歴史、文化、暮らしの記憶が凝縮された物語です。
「ベビー・ベンツ」に青春を託した若者もいれば、「タクシー・キング」に家族を預けた市民もいた。呼び名を知ることは、その国の人々がメルセデスをどう受け止め、どんな時間を過ごしたかを知ることでもあります。
💡関連動画💡